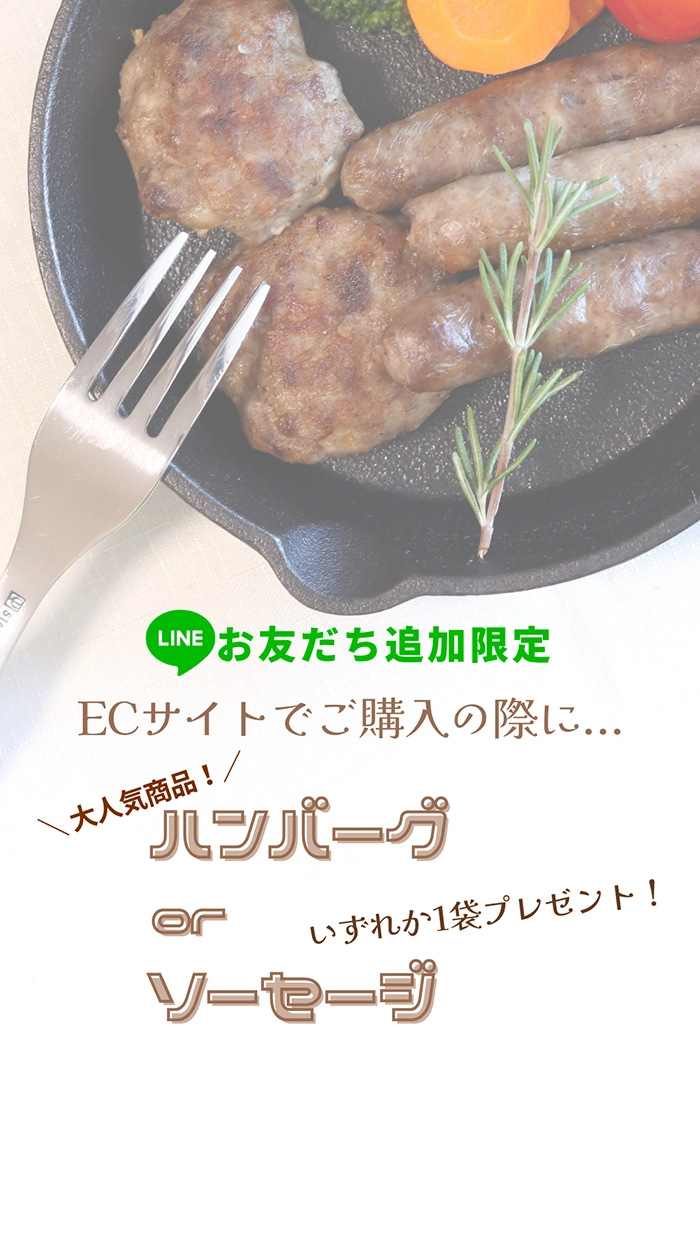ジビエの生食は危険!刺身やユッケがNGな理由と安全に楽しむコツ
2025.08.01目次 ー
近年、ジビエ料理が注目を集め、その独特の風味や栄養価の高さから、多くの人に楽しまれています。「新鮮だから刺身で食べてみたい」「ユッケ風にしたら美味しそう」と思う方もいるかもしれませんが、ジビエの生食は極めて危険です。
ジビエは自然の中で育った野生動物の肉であり、寄生虫や細菌による食中毒のリスクが非常に高いことで知られています。
この記事では、ジビエを生で食べてはいけない理由を、具体的な寄生虫や細菌の種類を交えて解説します。あわせて、安全に美味しく楽しむための調理ポイントも紹介しますので、ジビエ料理に挑戦したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ジビエを生で食べてはいけない理由

引用元:photoAC
ジビエとは、野生の鹿やイノシシ、クマなどを指し、私たちが日常的に食べる家畜の肉とはまったく異なるリスクを伴います。
ここでは、なぜジビエを生で食べてはいけないのか、その理由を詳しく解説します。
ジビエは家畜とは違いリスクが高い
ジビエに分類される野生動物は、自然の中で自由に生活しているため、寄生虫や細菌、ウイルスなどの病原体に日常的にさらされています。一方、牛や豚、鶏といった家畜は、衛生的な飼育環境で育てられ、病気の予防や健康管理が徹底されています。そのため、ジビエは家畜と比べて肉の安全性が格段に低く、特に生食による健康リスクが高いのです。
「新鮮だから安心」と思うかもしれませんが、見た目や臭いで病原体の有無を見分けることはできません。筋肉や内臓に寄生虫が潜んでいたり、肉に細菌が付着していたりする可能性があるため、生での摂取は非常に危険です。
厚生労働省も明確に生食を禁止
厚生労働省も、ジビエの生食については「加熱せずに食べるとE型肝炎ウイルスなどのウイルスや寄生虫に感染するおそれがある」と強く注意喚起しており、肉の中心部まで十分に火を通すよう求めています。
生のジビエに潜む寄生虫と細菌

引用元:photoAC
生のジビエには、人の健康に深刻な影響を及ぼす可能性のあるさまざまな寄生虫や細菌が潜んでいます。
適切な加熱処理によって死滅させることができますが、生食や加熱不足の場合、人体に感染し、重篤な健康被害を引き起こすリスクがあります。
引用元:photoAC ジビエ料理の人気が高まる一方で、寄生虫が気になる方もいるのではないでしょうか。ジビエにはなぜ寄生虫がいるのか、代表的な種類、安全に楽しむための調理法や衛生管理のポイントも紹介します。この記事を読んで、[…]
住肉胞子虫(サルコシスティス)
シカやイノシシ、クマの筋肉に寄生する微小な原虫です。感染すると、食後3〜6時間で吐き気、嘔吐、腹痛、下痢など急性胃腸炎に似た症状が出ることがあります。特に鹿肉でよく見られ、加熱不足は感染リスクを高めます。
旋毛虫(トリヒナ)
主にクマやイノシシに寄生する寄生虫で、感染すると最初に発熱や吐き気、下痢などの消化器症状が現れます。その後、幼虫が筋肉に移動し、激しい筋肉痛や関節痛、発疹、目の周りのむくみ(眼瞼浮腫)が起こります。重症化すると心臓や脳、肺にも影響し、最悪の場合は死に至ることもあります。治療が難しく、後遺症が残るケースもあります。
有鉤条虫(ゆうこうじょうちゅう)
イノシシや豚の肉に寄生するサナダムシの一種です。生や加熱不足の肉を食べると、腸内で成虫に成長します。感染すると腹痛や下痢、食欲不振が起こり、肛門から虫の一部が排出されることもあります。幼虫が腸壁を突き破って血流に入り、脳や目、筋肉などに移動し、てんかん発作や頭痛、視力障害、麻痺などの重い神経症状を引き起こす場合があります。
ウェステルマン肺吸虫
主にイノシシやカエルに寄生する寄生虫です。感染した肉を生食または加熱不足で食べると人に感染します。体内で幼虫が肺に移動して成虫となり、咳や血痰、胸の痛み、呼吸困難などの症状を引き起こします。
E型肝炎ウイルス
イノシシやシカの肉から検出されることがあるウイルスで、感染すると発熱や腹痛などのE型肝炎を発症します。ほとんどは自然治癒しますが、妊婦や高齢者は重症化しやすく、命に関わる場合もあります。
サルモネラ菌
動物の腸に広く存在し、肉の処理過程で表面に付着します。感染すると6〜48時間後に激しい腹痛、下痢、発熱、嘔吐を引き起こします。症状は数日続き、免疫力が低い人は敗血症になるなど重症化する恐れがあります。
腸管出血性大腸菌(O157など)
牛などの家畜だけでなく、野生動物の腸にも存在します。感染すると激しい腹痛や水様性下痢を起こし、血便が出ることもあります。特に乳幼児や高齢者、免疫力が弱い人は溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症し、腎不全や神経障害を引き起こし命に関わることもあります。
カンピロバクター
鶏や豚、野生動物の腸に広く存在する細菌です。感染すると下痢、腹痛、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛などの症状が出ます。少量の菌でも感染しやすく、潜伏期間は2〜5日です。まれにギラン・バレー症候群という自己免疫疾患を引き起こし、麻痺などの神経症状が現れることがあります。
生のジビエを食べたことによる食中毒の事例

引用元:photoAC
2016年に、野外で捕獲されたクマの肉が原因で旋毛虫による食中毒が発生しました。
狩猟者が許可を受けていない施設でクマを解体し、その肉を譲り受けた飲食店が加熱が不十分なローストとして提供したことが原因と考えられています。
この食中毒では複数の患者が旋毛虫に感染し、発熱や筋肉痛などの症状を訴えました。
この事例からも、ジビエは捕獲後の適切な処理や、飲食店での正しい調理が非常に重要であることがわかります。国のガイドラインに従い、衛生管理を徹底し、肉の中心まで十分に加熱することを必ず守りましょう。
ジビエ肉を安全に食べるためのポイント

引用元:photoAC
ジビエ肉を安心して美味しく楽しむためには、いくつかの重要なポイントを守ることが欠かせません。適切な処理や加熱、衛生管理を徹底することで、寄生虫や細菌によるリスクを大幅に減らせます。以下で具体的なポイントを解説します。
引用元:USA GIBIER FACTORY ジビエを楽しむ際、食あたりのリスクを心配される方も多いのではないでしょうか?この記事では、ジビエによる食あたりの原因や主なリスクについて詳しく解説します。また、予防のための調理法や保存方法[…]
処理済みのジビエ肉を選ぶ
まずは、国の認定を受けた食肉処理施設で適切に処理されたジビエ肉を選びましょう。こうした施設では衛生管理が徹底され、必要に応じて寄生虫検査なども行われています。購入の際は、パッケージの表示をよく確認し、信頼できる製品かどうかを見極めることが大切です。
中心温度75℃で1分以上の加熱を徹底
ジビエ肉は刺身やユッケなどの生食を避け、中心部までしっかり加熱することが必須です。厚生労働省の指針によると、肉の中心温度が75℃で1分以上加熱されていることが目安となります。肉の色が変わり、透明な肉汁が出るまでしっかり火を通しましょう。厚みのある肉は、温度計で中心温度を測るとより確実です。
調理器具の衛生管理
生肉を扱った包丁やまな板、トングなどは、他の食材用とは分けて使用しましょう。使用後は熱湯消毒や塩素系漂白剤、食器用洗剤でしっかり洗浄することが重要です。また、生肉に触れた後や調理中は、石鹸で手を丁寧に洗う習慣をつけることで、食中毒のリスクをさらに減らせます。
ジビエをさらにおいしく調理するコツ

引用元:USA GIBIER FACTORY
安全に調理するだけでなく、ジビエをさらにおいしく調理するためのコツもご紹介します。
引用元:USA GIBIER FACTORY 自然の恵みであるジビエは、独特の風味と高タンパク・低脂質・鉄分豊富といった栄養価の高さから、近年では健康志向の人々やアウトドア愛好家を中心に注目を集めています。また、持続可能な食材[…]
解凍は冷蔵庫でゆっくり
冷凍されたジビエ肉を調理する際は、調理の前に冷蔵庫でゆっくりと完全に解凍することが重要です。急いで解凍すると肉の旨味成分が流れ出しやすくなり、味が落ちてしまいます。
半解凍の状態で加熱すると、肉の内部まで熱が伝わりにくく、生焼けの原因になったり、肉が硬くなったりすることがあります。冷蔵庫で一晩かけて解凍するのがおすすめです。
お酒や牛乳に漬け込んで臭みを軽減
ジビエ肉特有の風味が気になる場合は、調理前に牛乳や赤ワイン、日本酒などに数時間から一晩程度漬け込むと効果的です。牛乳のタンパク質は肉の繊維を柔らかくし、お酒の香りはジビエの風味をまろやかに整えます。
肉の種類や厚みによって漬け込み時間を調整しましょう。
弱火でじっくりと焼く
ジビエ肉は、特に赤身が多い場合、強火で一気に焼くと肉の表面だけが焦げ付き、中心が生焼けになったり、肉の水分が失われて硬くなりがちです。
肉の旨味を閉じ込め、しっとりと柔らかく仕上げるには、弱火でじっくりと時間をかけて焼くのがおすすめです。ローストや煮込み料理も、低温で長時間加熱することで、肉の繊維がゆっくりとほぐれ、より美味しく仕上がります。焦らず、肉の状態を見ながら丁寧に火を通しましょう。
まとめ

引用元:USA GIBIER FACTORY
ジビエを生で食べるのは、とても危険です。野生の動物の肉には、健康を害する寄生虫や細菌がいることが多いため、必ず避けましょう。ジビエを安全に楽しむためには、国の基準に従ってしっかりと処理された肉を選び、中心まで十分に火を通すことが大切です。
ぜひ、今回ご紹介した安全に食べるためのポイントと調理のコツを参考に、ジビエ本来の奥深い味わいを堪能してください。
この記事で紹介した安全に食べるポイントや調理のコツを参考にして、ジビエの美味しさを安心して味わってください。
安心できるジビエをお探しなら、宇佐ジビエファクトリーがおすすめです。捕獲から解体、加工まで厳しい衛生管理のもとで行われており、専門家が臭みを抑えたおいしいジビエを提供しています。興味がある方は、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください。